
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
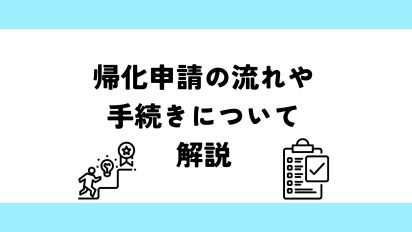
目次
帰化を希望する場合、手続きの流れや具体的な審査期間について気になる点が多いでしょう。帰化申請は法務局において必要な書類を提出し、面接を受けて、日本国籍を取得するための審査が行われます。
このプロセスは、帰化を希望する方の属性や状況によって異なるため、各ステップにおいて必要な確認をしっかり行うことが重要です。本記事では、帰化申請の手続きの流れや必要書類、さらには注意すべき点について整理していきます。
必要書類の収集や手続きに関する情報をもとに、具体的な手順を明確にすることで、皆さんが帰化申請をスムーズに進められるようにお手伝いします。
本記事では帰化申請の流れ、所要時間、そして審査結果が出た後の対処法についても詳しく解説いたします。
帰化申請を行う前に、自身が満たすべき帰化要件と条件を確認することが重要です。一般的に、帰化の要件は申請者の属性によって異なります。例えば、特別永住者であれば3年の居住歴が求められますが、日本人や永住者の家族は18歳未満でも申請が可能です。
申請者は大きく3つのグループに分けられます。特別永住者、日本人と結婚した外国人、一般の在留資格を持つ者です。まず、自分が普通帰化か簡易帰化に該当するかを見極める必要があります。その後、事前相談によって自分の状況を整理することが望ましいです。
相談時には、自身の独身や既婚、同居の状況、経済的状態などを把握しておくことが役立ちます。また、帰化後に使いたい名前や苗字についてもこの段階で考えておくと良いでしょう。帰化要件を確認し、相談準備を整えることで、よりスムーズな手続きへとつながります。
※法務省:https://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html
条件について:https://visa.go-al.co.jp/contents/contents_post-1971/
事前相談が終了した後、申請者は「必要書類一覧」を受け取り、申請書の作成に進みます。龍谷大学の調査によると、帰化申請の過程で最も手間がかかるのは書類集めです。これに必要な書類は11~13種類で、申請者の情報を詳細に申請書に記載する必要があります。
特に記入が難しいとされるのは、履歴書(その1)と履歴書(その2)です。履歴書(その1)では、学歴や職歴、居住歴、身分関係を時系列で記入しますが、通常の履歴書とは異なる形式で提出が求められるため、戸惑うことが多いです。
法務省が公表している帰化申請の必要書類のリストです。
引用記事:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a11
帰化の書類は、法務局に事前相談した後に、個別に必要となる書類が指示されます。
書類は、かなり種類が多く混乱しやすいため、大きく3つに分けて考えると、書類作成等の準備や収集がしやすくなるでしょう。
帰化申請の書類作成は、多い人で100種類以上も必要であるため、収集で困らないように、行政書士の方と相談しながら準備することをおすすめいたします。
なお、書類は、帰化申請者の職業、国籍などによって種類は異なります。職業別では、会社員、個人事業主、経営者によって必要書類は異なります。
また、国籍に係わる書類の中で「国籍証明書」は、世界共通の書類ではないため、国ごとに代替えとなる書類を提出することになります。他にも、家族関係や学歴、個々のケースによって、必要となる書類が変わってきます。
書類の収集では、入手に時間のかかるものから順に取り寄せていくと良いでしょう。
本国に関する書類は、在日領事館で取り寄せられる書類もありますが、本国から郵送しなければならない書類は、優先して収集等の準備すると良いでしょう。
では、帰化申請の必要書類とその詳細は、以下の一覧表で確認していきましょう。
| 作成する必要書類 | 提出書類の例 | ||
| 1.帰化許可申請書 | 帰化許可申請書 | ||
| 6か月以内に撮影の5cm×5cmの写真 | |||
| 2.親族の概要を記載した書類 | 親族概要書 | ||
| 3. 帰化の動機書 | 申請人本人の自筆書類 | ||
| ※特別永住者は免除される | |||
| 4. 履歴書 | 最終卒業証明書または卒業証書 | ||
| 在学証明書(在学中の場合) | |||
| 成績証明書(在学中の場合) | |||
| 資格証明書のコピー | |||
| 閉鎖外国人登録原票 | |||
| 外国人登録原票 | |||
| 出入国記録 | |||
| 5. 生計の概要を記載した書類 | 在勤証明書 | ||
| 給与証明書 | |||
| 土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本) | |||
| 預貯金現在高証明書・預貯金通帳のコピー | |||
| 賃貸契約書のコピー | |||
| 6. 事業の概要を記載した書類 | 個人事業主 | 経営者 | |
| 所得税の納税証明書 | 法人の登記事項証明書 | ||
| 消費税納税証明書 | 法人税納税証明書 | ||
| 事業税納税証明書 | 消費税納税証明書 | ||
| 営業許可証のコピー | 事業税納税証明書 | ||
| 確定申告書のコピー | 都・県・市・民納税証明書 | ||
| 源泉所得税の納付書のコピー | 経営者個人の所得税納税証明書 | ||
| 源泉徴収簿のコピー | 厚生年金保険料領収書のコピー | ||
| 修正申告書のコピー | 厚生年金加入届のコピー | ||
| 貸借対照表・損益計算書 | 営業許可証のコピー | ||
| 経営者としての確定申告書のコピー | |||
| 法人の確定申告書のコピー | |||
| 源泉所得税の納付書のコピー | |||
| 源泉徴収簿のコピー | |||
| 修正申告書控えのコピー | |||
| 貸借対照表・損益計算書 | |||
| 7. 住民票 | 住民票コピー | ||
| 8. 国籍を証明する書類 ※日本語翻訳を添付 | 国籍証明書 | ||
| 国籍の離脱または喪失証明書 | |||
| 出生証明書(国際証明書が取得できない場合) | |||
| パスポート | |||
| 9. 親族関係を証明する書類 ※本国書類は翻訳者の記名と押印 | 中国語 | 韓国語 | その他の外国人 |
| 出生公証書 | 基本事項証明書 | 出生証明書 | |
| 親族関係公証書 | 家族関係証明書 | 婚姻証明書 | |
| 結婚公証書 | 婚姻関係証明書 | 離婚証明書 | |
| 離婚公証書 | 入養関係証明書 | 親族関係証明書 | |
| 養子公証書 | 親養子入要関係証明書 | 国籍証明書 | |
| 死亡公証書 | 除籍謄本 | 死亡証明書 | |
| 10. 納税を証明する書類 | 個人 | 個人事業主 | 法人 |
| 源泉徴収票 | 源泉徴収票 | 住民税の納税証明書 | |
| 非課税証明書 | 非課税証明書 | 法人事業税の納付証明書 | |
| 住民税の納税証明書 | 住民税の納税証明書 | 法人税の納付証明書 | |
| 所得税の納税証明書 | 所得税の納税証明書 | 消費税の納税証明書 | |
| 確定申告の控え | 消費税の納税証明書 | 法人税の確定申告控え | |
| 確定申告の控え | 源泉徴収簿の写し | ||
| 源泉徴収納付書と領収書 | 年金保険料の納付証明書 | ||
| 11. 収入を証明する書類 | 在勤証明書 | ||
| 給与証明書 | |||
| 源泉徴収票 | |||
| その他の書類 | 宣誓書※事前準備は不要、申請受付時に自筆で署名 | ||
| 自動車運転免許証コピー | |||
| 運転記録証明書 | |||
| 運転免許経歴証明書 | |||
| 自宅付近の略図 | |||
| 勤務先付近の略図 |
一覧表での項目は、法務省が公表している11種類の書類に対して、一般的に必要となる内容になります。一覧表以外で個別に追加書類が求められた場合は、随時対応するようになります。
帰化申請の必要書類に関しては、申請前に法務局で必要書類の確認と点検を個別に行っています。帰化申請が許可されるまでに、何回か法務局に出向いて相談と確認を繰り返すことになります。
以下の表では、帰化書類を取り寄せる入手場所について確認できます。
| 出入国在留管理庁 | 役所 | 税務署 |
| 閉鎖外国人登録原票 | 住民票 | 所得税の納税証明書 |
| 外国人登録原票 | 戸籍謄本 | 消費税の納税証明書 |
| 出入国記録 | 住民税の納税証明書 | 事業税の納税証明書 |
| 法務局 | 住民税の課税証明書 | 法人税の納税証明書 |
| 土地・建物登記事項証明書 | 非課税証明書 | 消費税の納税証明書 |
| 法人の登記事項証明書 | 法人都・県・市・民税納税証明書 | |
| 警察署 | 自動車安全運転センター | 在籍校 |
| 運転免許経歴証明書 | 運転記録証明書 | 最終学歴の卒業証明書 |
| 年金事務所 | 勤務先 | 在学証明書 |
| 国民年金保険料納付確認書 | 源泉徴収票 | 成績証明書 |
| 年金保険料領収証 | 在勤証明書 | 在日大使館・領事館 |
| 給与証明書 | 国籍証明書 | |
| 韓国領事館 | 中国の公証処 | |
| 親族関係を証明する書類 | 親族関係を証明する書類 |
※法務局:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00891.html
帰化申請の手続きは、およそ以下の流れになります。
では、各ステップごとに解説していきます。
法務局へ帰化の事前相談のために予約をします。予約先は、以下の法務局のwebサイトより、住所を管轄している対象の法務局・地方法務局あてに連絡し、受付をしましょう。
帰化相談の予約先 法務省:国籍に関する相談窓口一覧(帰化、国籍取得、重国籍など)
なお、予約制ではない地方法務局もありますので、事前に確認しましょう。
※法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00887.html
帰化申請を進めるための第一歩として、申請人の居住地を管轄する法務局または地方法務局に相談することが不可欠です。帰化申請には必要な書類が多岐にわたり、国籍や家族構成によって異なるため、個別の確認が重要です。法務局に行く前に必ず予約を取りましょう。特に、大きな都市の法務局では、予約が取りにくく、場合によっては数ヶ月先まで埋まっていることもあります。
法務局の相談では、自分の在留資格や日本に来た経緯、家族構成、さらに犯罪歴などに関する情報を尋ねられます。これらの情報をもとに、帰化要件を満たしているかどうかが判断され、クリアであれば必要書類が告げられます。なお、法務局によっては予約の際に要件を簡単に確認することもあるため、その際にも注意が必要です。要件を満たしていない場合、相談を受け付けてもらえないことがあります。
東京法務局で初めて相談を受ける方は、「帰化相談質問票」をダウンロード・プリントアウトして、あらかじめ記入したものを持参します。
詳しい内容は、帰化相談:法務局
法務局から指示された必要書類の収集を始めます。帰化申請の中でも一番手間と時間がかかるのが帰化書類の収集です。多い人で100種類以上の書類が必要になる場合もあります。帰化に必要な書類は、申請者の状況や国籍、属性などによって異なり、書類の入手先もいろいろになってきますので整理しながら進めて行きましょう。
事前に必要書類を収集した後、法務局に出向き帰化申請書類の作成を行います。申請書を含む約10枚前後の資料を、丁寧に記入しなければなりません。記載内容に誤りがあると、申請が許可されない可能性が高くなるため、注意が必要です。
法務局で提供される申請書は手書き専用であり、修正液の使用は認められていません。そのため、記載時には慎重を期すべきです。記入方法については、法務局から配布される「帰化の手引き」を参考にして、正確に記入することが求められます。
帰化申請書類には、個人情報としての名前や住所だけでなく、在留状況や職歴、収入源に関する情報も含まれるため、これらの情報が他の提出書類と整合性を持つよう注意を払うことが重要です。
収集した書類を持参して、再度法務局に予約を入れ、書類確認を行います。この際、書類に不備がないか、または追加書類が必要かを担当官がチェックします。この際に、新たに必要な書類が指摘されることがあります。提出書類に不備がなければ、通常この時点で帰化申請が受理されます。しかし、書類が受理されたからといって、必ずしも帰化許可が下りるわけではないため、その後のプロセスにも注意が必要です。
再提出の場合、不足した書類や間違い部分を直します。再び法務局に予約を入れて、申請者全員で法務局に行くことになります。ここで不備があれば、同じ作業を繰り返す状態に陥る可能性もあるので、注意しましょう。
国籍離脱が事前に必要な場合は、法務局から指示されます。中国籍、韓国籍の方は、事前の国籍離脱は不要ですが、台湾国籍、ベトナム国籍の方は事前の国籍離脱が必要になります。国籍離脱の手続きをした際は、帰化申請で国籍の離脱または喪失証明書を提出します。
申請者本人は法務局の窓口へ行って帰化申請書と必要書類を提出します。申請者が15歳未満のときは、両親などの代理人が手続きを行います。なお、申請が受理されても許可/不許可の結果はこの時点ではわかりません。受理されても不許可となる場合もあります。申請手数料はかかりません。
申請が受理されてから2~3ヵ月後、法務局から面接の連絡が届きます。指定された日時に法務局へ出向き、面接・面談を受けることになります。
面接では、申請書や書類に基づいて疑問点や現在の状況について質問を受けます。質問内容は個々の状況によって異なりますが、事実を率直に答えれば問題ありません。なお、日本に住む配偶者や家族がいる場合、彼らも面接に参加することになります。配偶者と申請者の面接は別々の部屋で行われるため、互いに話をすることはありません。
面接中は適切なマナーや言葉遣いが求められるため、丁寧に対応することが重要です。これにより、審査における印象が良くなります。また、帰化申請は重要な手続きであるため、十分に準備して臨むことが求められます。
審査期間中は、法務局から申請者の勤務先、学校などに確認の電話が入ることや、実際に自宅に訪問してくるケースもあります。また、法務局から出頭要請や追加書類の指示があった場合には、随時対応するようになります。審査期間は、だいたい1年程度となりますが、場合によっては2年程度かかることもあります。
審査中に、帰化申請書に記入した内容の変更があった場合は、随時、変更内容を法務局に知らせる必要があります。引越しや転職の際は必ず連絡し、審査官の指示に従ってください。
地方法務局で帰化申請に必要な書類が確認され、条件を満たしていると判断されると、その書類は次に法務省に送付されます。このプロセスの重要な部分は、法務省が国籍取得の最終的な判断を行うことです。
法務大臣が書類を精査し、申請者の適格性や必要条件が全て揃っているかを判断します。このため、法務局からの書類送付は、帰化申請のプロセスにおいて極めて重要なステップと言えます。
さらに、法務省への書類送付後は審査が進行し、最終的には許可または不許可の決定が下されます。申請者には、この段階から期待感と不安が交錯することでしょう。
帰化申請の結果が決定します。許可された場合、申請者の名前が官報に掲載され、その後、法務局の担当者から電話連絡が行われます。一方、不許可の場合は、「不許可通知書」が郵送され、申請者にその決定が伝えられます。
申請から結果通知までの期間は、一般的に1年程度かかります。この間、法務局からの連絡を待つことになります。
帰化が不許可の場合、法務局から「不許可通知書」が本人宛に届きます。
「不許可通知書」には、帰化申請を不許可と決定した旨が記載されています。帰化が不許可となった場合は、再申請も可能ですが、まずは不許可になった理由を解消します。
再申請の際は一度専門家に相談し、アドバイスを受けて再度チャレンジするかどうか検討できます。
帰化が許可された方は、法務局から指定された日時に出頭する必要があります。当日は「帰化許可通知書」及び「身分証明書」を受け取ります。この書類は日本国籍取得の重要な証明となります。
受け取った書類は、住所を管轄する役所に持参することで戸籍が編製される手続きが行えます。また、在留カードを所持している場合は、住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。
なお、日本国籍取得後にも戸籍やパスポートなどの手続きが必要ですので、事前に確認しておくと良いでしょう。手続きの流れを正確に理解し、着実に進めることが大切です。
全員では無いですが、日本語テストを受けることも可能性があります。だいたい、帰化申請者の大体10%前後と言われています。
事前相談あるいは面接での日本語での会話がスムーズに行えなかった場合にテストを受けなければならない場合があります。小学校3年生(日本語能力テストN3)程度のレベルです。
もし日本語での会話やテスト、面接に不安を抱えている場合、帰化申請をする前から勉強しておく必要があり、注意すべき点です。
普通帰化は、一般的に外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きであり、多くの方がこのプロセスを選択することになります。帰化を希望する外国籍の方は、次の7つの条件をすべて満たす必要があります。これには、居住年数、納税義務の履行、法的能力の確認、日本語能力、さらには、日本の文化や社会への理解度も含まれます。これらの条件は、帰化が日本社会に適応するための大切な基盤を形成しています。条件を十分に理解し、準備が整った上で、正式に帰化申請を行うことが求められます。
簡易帰化とは、日本国籍を取得するための特例として存在する制度の一つで、特定の条件を満たすことで、通常よりも手続きが簡略化された形で帰化申請ができます。しかし、その許可が下りるまでの期間はどのくらいなのでしょうか。一般的に、帰化申請の許可が下りるまでの時間は、申請から約6ヶ月から1年程度とされていますが、易帰化の場合はこれよりも短い期間で許可が下りることが多いと言われています。
なぜなら、簡易帰化の場合は、通常の帰化申請に比べて提出する書類が少なく、審査も効率的に行われるためです。
通常、簡易帰化の申請から許可までの期間は、6ヶ月程度となります。しかし、これはあくまで一般的な目安であり、個々のケースにより異なることを理解しておくことが重要です。申請者の状況や準備した書類の内容、法務局の審査の状況など、様々な要素が許可までの期間に影響を与えます。
帰化許可された後も、手続きは続きます。
法務局より交付された帰化の「身分証明書」を持参して、居住地の市町村役場で「帰化届」を提出します。「帰化届」を行うと晴れて日本国籍を取得したことになります。
また、今まで所持していた「在留カード」または「特別永住者カード」は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所へ直接持参、または、郵送で返納します。
他にも、日本のパスポート取得、運転免許証の変更手続き、銀行口座や公共料金など、各種名義変更の手続きは、日本国籍者として新たに登録または変更手続きを行います。
帰化申請を進めるにあたり、特に注意が必要なポイントがいくつか存在します。まず、申請書類の記入においては、正確さが求められます。誤った情報や不備があると、申し込みが不許可となる可能性が高まりますので、基本情報の確認を怠らないことが重要です。
次に、提出期限を守ることが不可欠です。期限を過ぎることで、プロセス全体に遅延が生じるリスクがあります。加えて、帰化許可後にも必要な手続きがあるため、事前に必要書類を詳細に調査することが推奨されます。特に時間がかかる警察証明書や健康診断書などは早めに準備することが望ましいです。
また、帰化後の手続きや関連する費用についても把握しておく必要があります。一度限りの申請であることを考慮し、慎重に進めることが大切です。これらの準備をしっかりと行うことで、スムーズな帰化申請が可能となります。トラブルを避け、必要書類を適切に収集することで、帰化プロセスを円滑に進めることが期待されます。
帰化申請の際には、申請者の人格や行動、生活態度などが総合的に評価されます。その一環として、犯罪歴も重要な審査項目となります。したがって、犯罪歴を持つ者が帰化申請を行う場合、その詳細や反省の態度、更生の努力などが問われることになります。犯罪歴があるからといって、一概に帰化申請が不可能とは言えませんが、その犯罪の内容や時期、回数などにより、審査の結果は左右されるでしょう。
また、申請者が犯罪を犯した背景や理由、その後の生活状況、更生の取り組みなども考慮されます。反社会的な行為を繰り返している者や、薬物依存など治療が必要な状況にある者は、帰化申請が難しくなる可能性があります。一方で、過去に一度だけ軽微な犯罪を犯し、その後は法律を守り、社会的な信用を得ている者なら、帰化申請が許可される場合もあります。
帰化申請は、日本社会に適応し、法を守り、社会的な信用を得ているかどうかが重要な判断基準となります。そのため、犯罪歴を持つ者でも、その後の行動や態度により、帰化申請が可能な場合もあるということを覚えておきましょう。しかし、犯罪歴がある場合は、専門家に相談し、適切な申請書類の準備や説明をすることが求められます。
※法務局:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00885.html
以上が、帰化申請の流れになります。
帰化申請では、法務局との相談から帰化許可となるまでを「自分でする」または「行政書士に依頼する」のいずれかを選んで行うことができますが、帰化条件を証明するために、たくさんの書類を提出しなくてはなりません。
書類の準備は、個人では収集に時間や手間がかかるため、帰化申請のプロにサポートを受けながら手続きを進めることをお勧めします。
行政書士GOALではお客様の帰化申請について、専門チームが親身になって対応させて頂きます。ご連絡をお待ちしております。
A. 帰化申請に影響があるかどうかは、その違反の内容と回数によります。直近5年間で軽微な違反が3回以下であれば、通常は申請に大きな障害とはなりません。しかし、5回以上の違反や免許停止のような重い刑事罰を受けた場合には、申請までに一定の期間を置くことが求められます。このように、具体的な違反の内容や回数によって対応が異なるため、事前に十分な確認が必要です。
A:同居人に安定的な収入があれば、帰化申請者が無職でも帰化できます。