
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
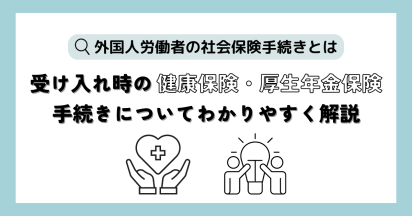
外国人労働者を受け入れるときの労働条件に関して、日本人労働者と差別的取扱いをすることは許されません。一方で、外国人労働者特有の手続きや制度があることも事業主としては認識しておく必要があるでしょう。
今回は、外国人労働者を受け入れるときの社会保険(健康保険・厚生年金保険)について解説していきます。
外国人労働者を受け入れるときの労働条件に関して、日本人労働者と差別的取扱いをすることは許されません。一方で、外国人労働者特有の手続きや制度があることも事業主としては認識しておく必要があるでしょう。
今回は、外国人労働者を受け入れるときの社会保険(健康保険・厚生年金保険)について解説していきます。
一般的に健康保険と厚生年金保険を総称して社会保険といいます。この2つの保険制度には原則として同時に加入することになっており、年齢などによる例外が一部あるものの、本人の希望でいずれか一方にのみ加入するようなことは認められません。
社会保険は、事業所単位で加入します。株式会社などの法人の事業所であれば役員一名の会社(いわゆる一人社長会社)でも強制加入です。また、個人事業であっても従業員5人以上であれば、農林漁業、サービス業などの一部の業種を除いて強制加入になります。このような社会保険に加入する事業所のことを「(社会保険の)適用事業所」といいます。
2022(令和4)年10月からは、いわゆる“士業”事務所について、従業員5人以上の場合には、強制加入の対象になりました。
| 【適用事業所の要件】 ・株式会社などの法人の事業所 ・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所 (旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除く) ・船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶 |
社会保険の加入要件は、外国人労働者も日本人労働者も変わりません。適用事業所で常時使用される人は、国籍に関係なく社会保険の適用を受けます(「(社会保険の)資格を取得する」といいます)。
ここでいう「常時使用される人」とは、労務の対価として事業主や法人から報酬を受け取るすべての人を指し、事業主のみの場合(一人社長法人)も含みます。
| 【被保険者の要件】 ・法人の常勤役員 ・正規雇用労働者 ・一定時間以上働く非正規雇用労働者(短時間労働者) |
基本的には、フルタイム勤務の正社員・正規雇用労働者であれば強制加入です。パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者に関しては原則として「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上」の場合に加入義務が発生します。
正規雇用労働者が一般的な「週40時間/月21日程度」の勤務であれば、「週30時間以上/月15日以上」勤務するパートタイマーやアルバイトについても厚生年金保険に加入させる義務が発生することになります。
なお、健康保険は75歳未満(75歳以降は後期高齢者医療制度)、厚生年金保険は70歳未満が対象です。
また、2016年10月以降、段階的に社会保険の加入対象者が拡大されており、従業員規模によっては、週の所定労働時間が20時間以上のパートタイマーやアルバイトも加入義務が発生する場合がありますので注意してください。
社会保険の適用事業所に雇い入れた場合であれば、外国人労働者も日本人労働者も被保険者となるための要件は同じです。
外国人労働者であっても社会保険に加入させる義務が発生しますから、万が一、加入させていない外国人労働者がいればそれは事業主の責任ということになります。
例え外国人労働者本人が希望しない場合でも日本の社会保険制度をしっかり説明し、資格取得手続きを行う必要があります。
このとき、外国人労働者特有の手続きや制度に関しても説明をして理解を得る必要があるでしょう。
その外国人労働者が長期間日本に滞在する予定であれば日本人労働者と同様の保障が受けられることや、短期間で帰国することを考えているのであれば、社会保障協定や脱退一時金に関してもあらかじめ周知しておくのが望ましいといえます。
外国人労働者の場合、社会保険料が高いという理由や短期間で母国に帰るという理由から、社会保険加入を希望しない(拒む)人がいますが、そのような理由で社会保険に加入しないことは認められません。
外国人労働者の社会保険未加入を認めた状態で年金機構の事業所調査の対象となった場合、本来の加入日に遡って加入手続きをすることになります。この遡り手続きは、外国人労働者が既に退職して帰国してしまった場合でも免れることはできません。最悪のケースでは、その外国人労働者の本人負担分の社会保険料までも事業主が負担することになることもあるので注意が必要です。
外国人労働者であっても社会保険の資格取得要件に該当する場合には、被保険者となることは既にお伝えした通りです。
外国人労働者が会社の社会保険に加入する要件に該当しない場合には、外国人労働者自身が住んでいる(住民票がある)市区町村窓口で国民健康保険の資格取得手続きを行う必要があります。 詳しくは、市区町村窓口へ問い合わせをするよう促すようにすると良いでしょう。
外国人労働者を雇い入れたときによく相談されることの一つに扶養家族(被扶養者)に関することがあります。
健康保険の被保険者になった外国人労働者に扶養家族がいる場合や扶養家族の追加があった場合、「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出することで、被保険者の家族を被扶養者として申請することができます。
被扶養者に該当すれば、その被扶養者の分も健康保険証が発行され健康保険の給付を受けることができます。被扶養者に該当する主な要件は、次の通りです。
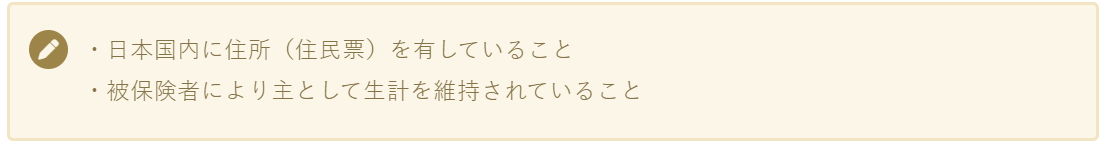
日本国内に住所がある場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する人は、被扶養者には該当しません。
被扶養者に該当するためには、日本国内に住所があることが要件となりますが、被扶養者となっている妻や子どもが、夫の海外転勤の同行家族として出国したり、海外勤務している被保険者と現地で結婚したりした場合には、一部例外があります。
*日本年金機構ホームページ
健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入は、同時に行うのが原則ですから資格取得要件に該当する場合には、日本年金機構に対して社会保険資格取得届を提出する必要があります。
社会保険被保険者資格取得届の氏名欄には、在留カードに記載されている通りに大文字で氏名を記入します。なお、ミドルネームについては「名」欄に記入してください。
このとき、外国人労働者については「資格取得時の本人確認」を行う必要があります。資格取得時の本人確認とは、個人番号(マイナンバー)を有している場合には、社会保険被保険者資格取得届に個人番号を記載することで本人確認が可能です。
被保険者のうちマイナンバーを有していない短期在留外国人などに関しては、次の書類の写しを社会保険被保険者資格取得届に添付して届け出ることで、本人確認を行います。
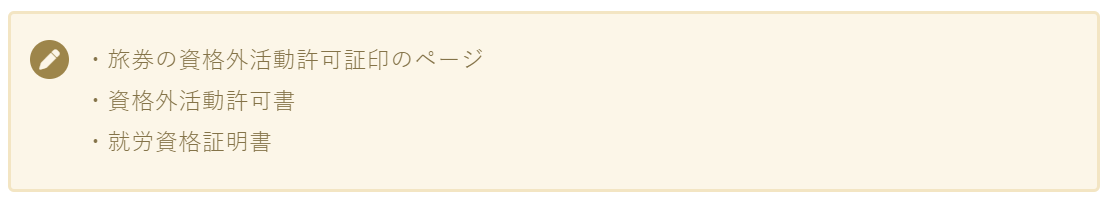
なお、マイナンバーの提示を受ける場合には、なりすましを防ぐため「マイナンバーカード(写真付き)」や「通知カード+運転免許証(身元確認)」等、本人確認が必要になります。
外国人労働者を雇い入れた場合でマイナンバーを持っていない場合やマイナンバーと基礎年金番号が結びついていない人に関しては、社会保険被保険者資格取得届と合わせて「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」を提出します。
このローマ字氏名届を提出するときには、在留カード、住民票の写し等に記載のある氏名を記入します。
外国人労働者を雇い入れる事業主としては、社会保障協定と脱退一時金という2つの制度の理解は必要不可欠であると言えます。詳しいことは専門家などにその都度確認するとしても概要だけは、理解しておく必要があるでしょう
外国人労働者が日本国内で就労する場合で社会保険の加入要件を満たすときには、事業主は社会保険被保険者資格取得手続きを行う必要があります。
日本の社会保険の加入要件を満たす一方で、母国の社会保険制度の加入も継続しているため社会保障制度の二重加入が発生してしまうケースがあります。
このようなケースを防ぐための制度が社会保障協定です。社会保障協定を締結している国から日本に働きに来ている外国人労働者であれば、原則として就労する国の社会保障制度のみに加入することになります。 なお、社会保障協定の内容は協定相手国によって若干の違いがある他、すべての国々と締結されているわけではありません。また、社会保障協定の締結国は、随時、更新されていますので詳細は、日本年金機構のホームページを確認してください。
*日本年金機構ホームページ
社会保障協定
日本の公的年金制度から老齢年金給付を受け取るためには、最短10年間、年金保険制度に加入した実績が必要ですが、実際には、10年に満たずに出国しその後、日本に戻ってくる予定が無い外国人労働者もいます。そのような短期在留外国人の年金保険料の掛け捨てを防止するための制度が脱退一時金です。
日本の公的年金制度に加入していた外国人労働者が社会保険被保険者資格を喪失(事業所を退職した場合など)して、日本を出国し、日本国内に住所が無くなった場合に納付した保険料の一部を脱退一時金として請求することができます。 厚生年金保険の脱退一時金を受け取るためには、加入期間が6箇月以上であることなどが条件となります。
*日本年金機構ホームページ
脱退一時金の制度
今回は、外国人労働者を受け入れるときの社会保険(健康保険・厚生年金保険)について解説してきました。
外国人労働者を受け入れる事業主としては、このようなことをしっかりと理解しておくことや、すぐに相談できる専門家との繋がりを持っておくことが必要不可欠です。
この記事に関するご相談、ご質問は、社会保険労務士法人GOALまでお問い合わせください。