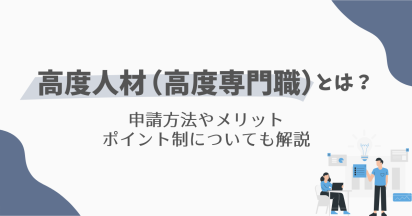日本で働く外国人の方、または外国人の雇用を考えている企業の人事担当者の方に向けて、在留資格「高度専門職」について解説します。高度専門職ビザは、日本の経済成長に貢献する優れた外国人材を積極的に受け入れるために創設された在留資格であり、他の就労ビザと比較して様々なメリットと優遇措置が用意されています。
本記事では、高度専門職の定義から取得に必要なポイント制、具体的な申請方法、そして取得後のメリットまで網羅的に説明します。
高度専門職の概要
高度専門職とは、日本において高度な知識や技術を持つ外国人材を指す在留資格です。この資格は、日本の経済成長や新たな需要の創出に貢献することが期待される優秀な外国人材の受け入れを促進する目的で創設されました。在留資格高度専門職を取得すると、様々な優遇措置が適用されます。活動内容に応じて、高度専門職1号のイ・ロ・ハ、そして高度専門職2号の4種類に分類されています。
高度専門職の定義
高度専門職とは、学術研究や経済の発展に貢献すると期待される、高度で専門的な能力を持つ外国人に与えられる在留資格です。具体的には、学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントを付与し、その合計が一定の点数に達した外国人に許可される制度となっています。
この制度は、優秀な外国人材の日本への受け入れを促進するために、高度人材ポイントによる評価システムとして導入されました。高度専門職の在留資格は、就労ビザの一種であり、通常の就労ビザに比べて活動制限が緩和されている点が特徴です。
高度専門職で認められる活動内容
高度専門職の在留資格では、その活動内容に応じて大きく3つのカテゴリーに分類される「高度専門職1号」と、それから移行する「高度専門職2号」が存在します。この在留資格の大きな特徴は、複合的な在留活動が許容されている点にあります。他の就労ビザでは原則として許可された一つの在留資格の範囲内でしか活動が認められませんが、高度専門職の外国人は、主たる活動に加えて関連する事業の経営活動も自ら行うことが可能です。
例えば、大学で研究活動を行いながら、その研究成果を活かした事業を経営するといった複数の活動が認められます。
高度学術研究活動(高度専門職1号イ)
高度専門職1号イは、「高度学術研究活動」を行う外国人向けの在留資格です。これは、日本の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導、または教育をする活動が対象となります。具体的には、大学の教授や、民間企業の研究機関における研究者などがこのカテゴリーに該当します。この在留資格では、取得した外国人に一律で5年の在留期間が付与されます。
さらに、本業である研究や教育活動に加えて、その成果を活かして事業を立ち上げ、自ら経営することも可能です。これは、高度な専門知識を持つ人材が、その能力を最大限に活かして日本の学術研究や経済発展に貢献することを目的としています。
高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)
高度専門職1号ロは「高度専門・技術活動」を行う外国人向けの在留資格です。このカテゴリーは、日本の公私の機関と契約に基づき、自然科学または人文科学分野における専門的な知識や技術を要する業務に従事する活動が対象となります。具体的には、企業での新製品開発に従事する技術者、ITエンジニア、企画立案業務、国際弁護士などが該当します。特にエンジニアとして日本で就労を希望する外国人にとって、この1号ロは主要な在留資格の選択肢の一つとなります。
この在留資格も同様に、主となる活動と併せて、これに関連する事業の経営活動を自ら行うことが許容されており、日本の産業発展に貢献する高度な専門技術を持つ人材の幅広い活躍が期待されています。
高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)
高度専門職1号ハは、「高度経営・管理活動」を行う外国人向けの在留資格です。このカテゴリーは、日本の公私の機関において事業の経営または管理に従事する活動が対象となります。具体的には、グローバルに事業を展開する企業の経営者や幹部、あるいは母国で相当な実績を持つ起業家などが該当します。
この在留資格は、主に企業の経営者や役員など、組織を管理する立場にある方を想定しており、他の在留資格では「経営・管理」に相当する活動内容となります。高度専門職1号ハの取得には、ポイント制の基準を満たすことに加えて、事業の規模や安定性も総合的に勘案され審査が行われます。
年収の最低基準額は300万円であり、年齢による年収基準はありませんが、ポイント加点される年収は最低1,000万円から最大3,000万円以上と設定されています。非常に高い専門性と経営手腕が求められるため、現時点での取得者は少数に留まっています。
高度専門職2号
高度専門職2号は、高度専門職1号の在留資格を既に取得し、日本で3年以上活動を行っていた外国人が変更を目指せる在留資格です。この在留資格の大きな特徴は、在留期間が無期限となる点にあります。高度専門職2号を取得すると、在留期間の更新手続きが不要となり、実質的に永住が可能となります。また、1号で認められる活動に加えて、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができるようになり、活動範囲が大幅に緩和されます。これにより、研究活動をしながら報道分野で活動するなど、自身の仕事や事業に対する選択肢が広がり、日本に継続して居住しながら、多様なキャリアを築けるという大きなメリットが得られます。
ただし、高度専門職2号は1号よりも要件や審査が厳しく、1号のメリットも継続して享受できますが、取得した在留資格の活動を6ヵ月以上継続しないまま在留すると、在留資格取消事由に該当する可能性があるため注意が必要です。
高度専門職の在留期間
高度専門職の在留期間は、その種類によって異なります。まず、高度専門職1号の在留期間は「5年」が一律に付与されます。これは、日本の現行制度において最長の在留期間であり、高度外国人材が安定的に日本で活動を継続できる環境を提供することを目指しています。5年の在留期間が認められるため、短期間での在留期間更新の負担が軽減され、企業側にとっても、長期的な雇用計画を立てやすいというメリットがあります。この期間は更新することも可能です。一方、高度専門職2号の在留期間は「無期限」となります。
高度専門職1号で3年以上日本に在留して活動を行っていた方が対象となり、この資格への移行が認められれば、以降の在留期間の更新許可を受ける必要がなくなります。これにより、高度専門職2号の保持者は、実質的に永住に近い形で日本に滞在し続けることが可能になります。在留カードの更新は7年ごとに行う必要がありますが、在留期間の心配がなく、日本での生活やキャリアをより安定的に築けるようになる点が大きな特徴です。
高度専門職と高度人材の違い
高度専門職と高度人材という言葉はしばしば混同されがちですが、厳密には異なる概念です。高度人材とは、専門的な技術力や知識を有する外国籍人材全般を指す広い概念であり、日本の労働市場において高い能力を持つ外国人労働者全体を指します。
一方、高度専門職は、この高度人材の中でも、法務省令で定められた一定の基準、具体的には高度人材ポイント制で合計70点以上のスコアを獲得した外国人に与えられる特定の在留資格を指します。つまり、すべての高度人材が高度専門職の在留資格を持っているわけではなく、高度専門職の在留資格を持つ外国人が高度外国人材と認定され、出入国管理上の様々な優遇措置を受けることができると定義されています。
高度専門職ビザが創設されたのは、より積極的に高度外国人材の受け入れを促進し、経済成長や新たな需要と雇用の創出に貢献してもらうことを目的としています。
※詳細はこちら
高度専門職の優遇措置
高度専門職の在留資格を取得すると、日本の経済発展に寄与することが期待される外国人材を積極的に受け入れるために、他の一般的な就労ビザにはない様々な優遇措置を受けることができます。これらのメリットは、本人だけでなく、彼らを雇用する企業側にとっても大きな利点となります。優遇措置は、主に高度専門職1号と高度専門職2号で内容が異なりますが、永住権取得要件の緩和、配偶者の就労、親や家事使用人の帯同、入国・在留審査の優先処理などが挙げられます。これらの措置により、高度外国人材はより安定した環境で日本での活動に専念でき、企業は優秀な人材を確保しやすくなります。
高度専門職1号の優遇内容
高度専門職1号の在留資格を持つ外国人材は、日本の経済発展への貢献が期待されるため、出入国管理上の様々な優遇措置が認められています。これらの優遇措置は、高度外国人材が日本でより円滑に、かつ長期的に活躍できる環境を提供することを目的としています。
複合的な在留活動の許容
高度専門職の在留資格で認められる活動内容の大きな特徴の一つに、「複合的な在留活動の許容」があります。通常の就労ビザでは、許可された一つの在留資格で認められている活動しか行うことができません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、許可された職務内容とは異なる事業の経営に携わる場合、別途「資格外活動許可」を取得する必要があります。
しかし、高度専門職の在留資格を持つ外国人は、主となる活動に加えて、その活動に関連する事業の経営活動を自ら行うことが認められています。これにより、例えば大学での研究活動を行いながら、その研究成果を活かした会社を立ち上げて経営するといった、複数の在留資格にまたがるような活動が可能です。この柔軟な活動範囲は、高度外国人材が自身の専門性や能力を最大限に活かし、多様な形で日本の経済や学術の発展に貢献できる大きなメリットとなります。
在留期間「5年」の付与
高度専門職1号の在留資格を取得した外国人材には、在留期間として一律「5年」が付与されます。これは、日本の現行制度において設定されている最長の在留期間であり、通常の就労ビザの在留期間が1年や3年である場合と比較して、非常に長い期間となります。この長期的な在留期間の付与は、高度外国人材が日本での生活やキャリアプランをより安定的に計画できるという大きなメリットをもたらします。
短期間での在留期間更新手続きの煩雑さから解放されることで、本業に集中しやすくなります。また、企業側にとっても、優秀な外国人材を長期的に雇用し、育成していく上で安定した基盤となり、人材の定着を促進する上で非常に有利な条件と言えます。この5年の期間は、その後も更新することができます。
永住権取得要件の緩和
高度専門職の在留資格を取得する外国人材にとって、特に大きなメリットの一つが永住権取得要件の緩和です。通常、永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされています。
しかし、高度専門職の在留資格を持つ外国人材、すなわち高度外国人材に認定された場合、この永住権取得までの在留期間が大幅に短縮されます。具体的には、高度人材ポイント計算表で70点以上の評価を得ている高度外国人材は、日本に継続して3年以上在留していれば永住許可申請の対象となります。
さらに、特に高度と認められる80点以上の評価を得ている高度外国人材の場合、わずか1年間の日本在留で永住許可申請が可能となります。この永住権取得要件の緩和は、日本での長期的なキャリア形成を視野に入れている外国人材にとって、非常に魅力的な優遇措置であり、日本への定着を促進する上で大きなインセンティブとなります。
配偶者の就労
高度専門職の在留資格を持つ外国人材の配偶者には、特別な就労に関する優遇措置が設けられています。通常、就労ビザで在留する外国人の配偶者は、「家族滞在」の在留資格で滞在し、別途「資格外活動許可」を得なければ就労はできません。さらに、その場合も週28時間以内という時間制限が設けられています。
しかし、高度専門職の外国人材の配偶者の場合は、「特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)」の在留資格を取得することで、学歴や職歴などの要件を満たさなくても、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行(演劇等の活動以外の芸能活動)」に該当する就労活動を時間制限なくフルタイムで行うことが認められています。これは、配偶者も日本でキャリアを築き、世帯収入を増やすことができるという大きなメリットであり、高度外国人材の日本での生活の安定と定着を強力にサポートする制度です。
ただし、この特定活動(33号)を取得するには、高度専門職本人と配偶者の同居が前提となります。また、配偶者が日本で働くことを希望していること、日本人と同等額以上の報酬を得る就労契約があること、在留中も同居が継続していることなどが条件となります。
親の帯同条件
高度専門職の在留資格を持つ外国人材には、親の日本への帯同が認められるという、他の就労ビザでは非常に珍しい優遇措置があります。通常、就労目的で在留する外国人の親の受け入れは認められていませんが、高度外国人材の場合は、以下のいずれかの条件を満たす場合に、本人またはその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が許可されます。
一つは、高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子ども(養子を含む)を養育する場合です。もう一つは、高度外国人材の妊娠中の配偶者、または妊娠中の高度外国人材本人の介助などを行う場合です。これらの条件に加えて、高度外国人材の世帯年収(本人とその配偶者の年収を合算した額)が800万円以上であること、そして親が高度外国人材と同居することが主な要件となります。この制度は、高度外国人材が日本で安心して子育てや家族のケアを行える環境を整備し、長期的な定着を促進することを目的としています。
家事使用人帯同の条件
高度専門職の在留資格を持つ外国人材は、一定の条件を満たすことで、家事使用人を日本に帯同することが認められています。これは、一般的に「経営・管理」や「法律・会計業務」などの在留資格を持つ一部の外国人にのみ認められている特例です。高度専門職の家事使用人の帯同には主に「入国帯同型」と「家庭事情型」の2つのタイプがあります。「入国帯同型」は、高度専門職外国人本人が海外で1年以上雇用していた家事使用人を日本に連れてくる場合で、原則として雇用主と共に来日し、雇用主と共に出国することが前提となります。日本での雇用主変更は認められません。
一方、「家庭事情型」は、高度専門職外国人の日本入国後に家事使用人を呼び寄せる場合や、日本で新たに雇用する場合に適用されます。このタイプでは、雇用主である高度専門職外国人に13歳未満の子どもがいる、または病気などにより日常の家事に従事できない配偶者がいるといった家庭の事情があることが条件となります。また、世帯年収が1,000万円以上であること(家事使用人2名の雇用を希望する場合は世帯年収3,000万円以上)、家事使用人の報酬が月額20万円以上であること、18歳以上であること、そして雇用主が使用する言語で日常会話ができることなどが共通の要件として求められます。
この制度は、多忙な高度外国人材が家庭生活と仕事を両立し、日本での生活をより豊かに送れるように支援することを目的としています。
入国・在留審査の優先処理
高度専門職の在留資格は、日本の経済発展に貢献する優秀な外国人材の受け入れを促進するため、その入国・在留審査において優先的な処理が行われる優遇措置が設けられています。入国事前審査に係る在留資格認定証明書交付申請については、申請受理から概ね10日以内を目途とされています。また、在留審査に係る在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の場合も、申請受理から概ね5日以内を目途に処理が進められるとされています。
ただし、これらの期間はあくまで目安であり、実際の審査期間は申請内容や状況によって異なります。2025年3月のデータでは、在留資格認定証明書交付申請で平均50日前後、在留期間更新許可申請で平均24日〜57日、在留資格変更許可申請で平均34日〜66日を要しています。
これは、他の一般的な在留資格の審査期間と比較して、優先的な処理が行われる傾向にあり、外国人材が日本での活動を迅速に開始できるだけでなく、企業側にとっても、優秀な人材のスムーズな受け入れを可能にする大きなメリットとなります。 迅速な審査プロセスは、外国人材の不安を軽減し、日本への移住・定着を後押しする重要な要素となっています。
高度専門職2号の優遇内容
高度専門職2号の在留資格は、高度専門職1号の保有者が日本に3年以上在留し、活動を継続した場合に移行できる在留資格であり、1号よりもさらに手厚い優遇措置が受けられます。
まず、最大のメリットは①在留期間が「無期限」になることです。これにより、在留期間の更新手続きが不要となり、実質的に日本での永住が可能となります。永住権とは異なるものの、高度専門職としての活動を継続している限り、期間を気にすることなく日本に滞在できます。
また、②活動範囲が大幅に拡大し、高度専門職1号で認められる活動に加えて、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができるようになります。これにより、研究活動をしながら他の分野で働くなど、多様なキャリアパスを選択できるようになります。
さらに、③高度専門職1号で認められていた永住権取得要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同、入国・在留審査の優先処理といった優遇措置も、高度専門職2号に移行後も継続して享受できます。これらのメリットは、高度外国人材が日本での生活やキャリアをより安定させ、柔軟に活動できる基盤を提供し、長期的な定着を強力に促進します。
高度専門職の取得要件
高度専門職の在留資格を取得するためには、定められた要件を満たす必要があります。その中心となるのが「高度人材ポイント制度」です。この制度では、申請者の学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力などの項目ごとにポイントが設定されており、合計が一定の点数に達していることが必須となります。特に、年収は重要な要件の一つであり、具体的な報酬額がポイントに大きく影響します。また、職歴もポイント計算の対象となるため、これまでのキャリアも考慮されます。これらのポイントは計算表に基づいて算出され、基準となる点数をクリアする必要があります。
高度人材ポイント制度の概要
高度人材ポイント制度は、高度専門職の在留資格を取得するために必要となる、外国人材の能力を客観的に評価する制度です。この制度では、申請者の「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「日本語能力」「研究実績」などの項目にそれぞれ点数が設定されており、それらを合計したポイントが基準点に達しているかどうかが審査されます。具体的には、合計70点以上を獲得することが高度専門職1号の取得要件となります。
さらに、80点以上を獲得した場合は、永住権取得要件のさらなる緩和など、より手厚い優遇措置を受けることができます。ポイントの計算は、出入国在留管理庁が公開しているポイント計算表に基づいて行われ、例えば、学士号は10点、修士号は20点、博士号は30点といったように、学歴に応じて点数が加算されます。年収についても、年齢によって最低基準額が定められており、年収が高いほど得られるポイントも大きくなります。
この制度は、外国人材の専門性や能力を数値化することで、透明性のある評価基準を設け、日本の経済社会に貢献できる優秀な人材を効率的に受け入れることを目的としています。
※無料相談はこちら
高度専門職の申請手続き
高度専門職の在留資格を取得するための申請手続きは、日本に新規入国する場合と、既に日本に在留している場合とで流れが異なります。どちらのケースでも、必要書類の準備と提出が重要となります。
※詳細はこちら
新規入国の場合の手続き
日本に新規で高度専門職として入国する場合の申請手続きは、以下の流れで進められます。
在留資格認定証明書交付申請
新規入国の場合、まず日本で雇用する企業または代理人が、管轄の地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請では、高度専門職に該当することを証明するためのポイント計算表や、学歴・職歴、年収を証明する書類、雇用契約書の写し、会社の概要などが提出されます。この証明書は、外国人が日本に入国するために必要となるビザ(査証)の申請に必要不可欠な書類です。
高度専門職の在留資格認定証明書交付申請は、他のビザと比較して優先的に処理されるとされていますが、審査期間は申請内容によって異なり、必ずしも短期間で完了するとは限りません。入国事前審査においては申請受理から10日以内を目途とされていますが、実際の平均審査期間は20日以上となることもあり、近年では申請件数の増加により、さらに時間がかかる傾向にあります。実際に1ヶ月から1ヶ月半ほどを要するケースも複数あります。この段階で、申請人の高度専門職としての適合性が審査されます。
在留資格認定証明書の送付
在留資格認定証明書交付申請が許可されると、地方出入国在留管理局から申請を行った企業または代理人に「在留資格認定証明書」が送付されます。この証明書は、日本に入国しようとする外国人が、日本での在留資格の要件を満たしていることを法務大臣が認定したことを証明する重要な書類です。企業または代理人は、この証明書を速やかに日本に入国する外国人本人に郵送します。この証明書を受け取った外国人は、次のステップであるビザの取得手続きに進むことになります。
ビザの取得
在留資格認定証明書を受け取った外国人本人は、居住している国にある日本の在外公館(大使館または総領事館)で、日本に入国するためのビザ(査証)を申請します。この際、送付された在留資格認定証明書と、パスポート、ビザ申請書などの必要書類を提出します。在外公館でのビザ審査は、提出された書類と照合し、日本への入国の可否が判断されます。
在留資格認定証明書が既に交付されているため、原則としてビザの発給はスムーズに行われますが、在外公館によっては追加の書類提出を求められる場合もあります。ビザが発給されると、外国人材は日本への入国が可能となります。
来日と就労開始
ビザを取得した外国人は、日本に入国します。空港の入国審査の際に、パスポートにビザが貼付されていることを確認し、在留資格「高度専門職」の在留カードが交付されます。この在留カードは、日本での身分証明書として非常に重要であり、常に携帯する必要があります。在留カードの交付を受けたら、いよいよ日本での就労を開始することができます。来日後は、住居地の届出など、必要な手続きを忘れずに行い、高度専門職としての活動に専念することとなります。
日本に在留中の場合の手続き
既に日本に他の在留資格で在留している外国人が高度専門職の在留資格に変更する場合の手続きは、新規入国とは異なります。この場合は、在留資格変更許可申請を行います。
在留資格変更許可申請
現在日本に他の在留資格で在留している外国人が高度専門職への変更を希望する場合、住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」を行います。この申請では、現在の在留資格から高度専門職への変更を希望する理由、高度人材ポイント計算表、学歴・職歴・年収を証明する書類、雇用契約書の写し、勤務先の会社概要、パスポート、在留カードなどを提出します。ポイントが70点以上であること、そして変更後の勤務先が前の勤務先と同等以上の条件を満たしているかどうかが審査されます。
もし転職を伴う変更の場合、新しい勤務先での年収が前職より低くなったり、職務内容が変わったりすることで、ポイントが基準を下回る可能性もあるため注意が必要です。高度専門職への変更申請は、通常の在留資格変更申請に比べて優先的に処理される制度がありますが、審査期間は個別の事情によって異なります。提出資料に疑義がある場合や、追加の照会が必要な場合は、審査に1ヶ月から1ヶ月半程度を要するケースも存在します。
一方で、在留審査に係る申請については、申請受理から概ね5日以内を目途に審査が行われるとされていますが、これはあくまで目安であり、全ての申請に適用されるものではありません。
許可と就労開始
在留資格変更許可申請が認められると、出入国在留管理局から在留資格変更許可の通知が届きます。許可された場合、新たな在留資格「高度専門職」が記載された在留カードが交付されるか、または既存の在留カードの裏面に新しい情報が記載されます。これにより、高度専門職としての活動を開始することが可能となります。許可通知を受け取った後は、速やかに新しい在留カードを受け取り、就労を開始します。万が一、申請が不許可となった場合は、他の在留資格への変更を検討するか、不許可理由を解消して再申請を行う必要があります。
高度専門職の更新手続き
高度専門職の在留資格を持つ外国人材が、在留期間が終了した後も日本での活動を継続したい場合、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。高度専門職1号の場合、在留期間は原則5年ですが、この期間を過ぎても日本に滞在し続けるためには更新が必要です。更新申請は、在留期限の3ヶ月前から地方出入国在留管理局で行うことができます。
在留期間更新許可申請書
写真
パスポート
在留カードの提示
本邦で行おうとする活動に応じた資料
ポイント計算表
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
などが必要となります。特に、更新時にも高度人材ポイントが70点以上あること、また予定年収が300万円以上であることが必須条件とされています。
入国後に年齢ポイントの減少や年収の変動があった場合でも、直ちに在留資格が取り消されるわけではありませんが、更新時には改めて総合的な審査が行われるため、条件を維持できているか確認することが重要です。高度専門職の更新審査は通常の就労ビザよりも厳格な傾向があるため、最新の審査傾向を踏まえた書類準備が求められます。
まとめ
外国人の在留資格高度専門職は日本の経済や学術の発展に貢献する高度な能力を持つ外国人材を積極的に受け入れるために設けられた特別な在留資格です。この資格は高度人材ポイント制度に基づき学歴職歴年収などの項目で一定の点数を満たすことで取得できます。
高度専門職の在留資格を取得すると在留期間5年の付与高度専門職1号や無期限の在留高度専門職2号永住権取得要件の緩和複合的な在留活動の許容配偶者の就労親や家事使用人の帯同入国在留審査の優先処理など様々な優遇措置を受けることができます。
これらのメリットは外国人材が日本で安定した生活を送りながらその専門性を最大限に活かしキャリアを形成していく上で大きな支えとなります。日本で活躍したい外国人の方そして優秀な人材を雇用したい企業の人事担当者の方にとって高度専門職は非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
※無料相談はこちら
よくある質問
A. 在留期間更新時には再度ポイント計算が行われるため、継続して要件を満たす必要があります。特に、年齢によるポイント変動や転職による年収・職務内容の変化には注意が必要です。また、転職した際には在留資格変更許可申請を行います。
A. 高度専門職の配偶者は特定活動(33号)の在留資格で、学歴や職歴の要件を満たさずに特定の活動を時間制限なくフルタイムで就労できるという優遇措置があります。しかし、同居が前提条件であり、夫婦間の関係性や生計維持能力も審査対象となります。
A. 可能です。ただし、転職等で高度専門職の要件を満たさなくなった場合、他の就労ビザへの変更手続きが必要となり、その場合は通常の就労ビザの取得要件を満たす必要があります。このように、高度専門職の在留資格は多くのメリットがある一方で、その維持や変更には特有の条件や手続きが伴うため、個別の状況に応じた詳細な確認や専門家への相談が推奨されます。