
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
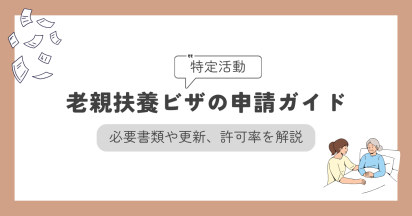
目次
海外で暮らす高齢の親を日本に呼び寄せ、自身の扶養のもとで共に生活したいと考える方のために、「老親扶養ビザ」と呼ばれる在留資格について解説します。正式には「特定活動」ビザの一種であり、法律に明確な定めがないため取得のハードルは非常に高いとされています。実際の許可率は公表されていませんが、取得が難しい在留資格の一つです。
この記事では、申請の要件や手続きの流れ、必要書類、条件、そして許可の可能性を高めるためのポイントまでを網羅的に説明します。
※無料相談はこちら
老親扶養ビザとは、海外に住む高齢の親を日本に呼び、扶養するために取得する在留資格を指す通称です。正式な在留資格の名称ではなく、出入国管理及び難民認定法に定められた「特定活動」という在留資格の一類型として扱われます。
これは、法務大臣が人道的な観点から特別な事情を考慮し、個々のケースごとに判断して付与するものです。そのため、明確な許可基準が法律で定められておらず、申請者の状況に応じて柔軟に審査される一方で、許可を得るためのハードルは非常に高いのが実情です。
※詳細はこちら
老親扶養ビザの取得は、他の在留資格と比較して著しく困難であると言われます。その背景には、この在留資格が持つ特殊な性質が関係しています。法律上の明確な根拠がないことに加え、国の社会保障制度への影響や、人道的な配慮の必要性が極めて厳格に審査されるためです。
ここでは、なぜこのビザの取得が難しいのか、その主な理由を3つの観点から掘り下げて説明します。これらの理由を理解することは、申請準備を進める上での重要な前提となります。
老親扶養を目的とする活動は、出入国管理及び難民認定法で定められた類型に当てはまらない「告示外」の特定活動に分類されます。これは、あらかじめ活動内容が定められている在留資格とは異なり、法務大臣が個別の事情を審査し、人道上の観点から特別に在留を認めるものです。したがって、申請にあたって参照できる明確な法律上の要件や基準が公開されていません。
申請者は、過去の許可事例などを参考にしつつも、自身のケースがいかに人道的な配慮に値するかを、一つひとつ証拠をもって立証していく必要があります。この点が、申請の難易度を著しく高める要因となっています。
高齢の親が日本で長期的に生活する場合、国民健康保険や介護保険といった日本の社会保障制度を利用することになります。これにより、国の医療費や介護給付費の負担が増加する可能性が考慮されます。そのため、出入国在留管理庁は、日本の公的負担増につながる可能性のある外国人高齢者の受け入れに対して、非常に慎重な姿勢で審査を行います。
扶養者となる子に、親の生活費だけでなく、将来的に発生しうる高額な医療費や介護費用まで含めて、すべてを私的に負担できるだけの十分な経済力があるかどうかが問われます。この経済的要件が、申請の大きなハードルの一つです。
この在留資格は、あくまでも人道的な配慮から例外的に許可されるものです。したがって、「親が高齢になったから一緒に暮らしたい」「親の面倒を見たい」といった一般的な親子間の情愛に基づく理由だけでは、許可を得ることは極めて困難です。
審査では、親が母国で一人で生活することが著しく困難であり、他に頼れる親族もいないため、日本にいる子が扶養する以外に方法がない、というような切迫した状況が求められます。つまり、客観的に見て、日本で扶養することが唯一の解決策であると認められるほどの、やむを得ない特別な事情の存在を証明しなければなりません。
老親扶養ビザの許可を得るためには、非常に厳格な要件を満たす必要があります。これらの要件は、日本に呼び寄せられる親自身に関するものと、日本で扶養する子に関するものの双方に及びます。具体的には、親の年齢や健康状態、本国での生活状況、そして扶養者である子の収入や資産状況、住環境などが総合的に審査されます。ここでは、許可判断の際に特に重要視される主な要件を、親側と扶養者側に分けて具体的に解説していきます。
親の年齢については、法律で明確な基準は定められていませんが、実務上は原則として70歳以上であることが一つの目安とされています。ただし、単に高齢であるだけでは十分な理由にはなりません。年齢に加えて、病気や身体的な障害などにより、他者の介助なしでは日常生活を送ることが困難な状態にあるといった、具体的な扶養の必要性を示すことが重要です。
この扶養の必要性は、医師の診断書や介護が必要であることを示す客観的な資料によって証明する必要があります。年齢が高くなるほど、また健康上の問題が深刻であるほど、扶養の必要性が高いと判断されやすくなります。
日本で扶養する必要性を証明する上で、本国に親を扶養できる人がいない、という状況が極めて重要な要件となります。具体的には、親の配偶者(呼び寄せる親の夫または妻)がすでに亡くなっていること、そして日本にいる申請者以外に、親の面倒を見ることができる兄弟姉妹やその他の近親者が本国にいないことが求められます。もし本国に他の子や親族がいる場合は、なぜその人たちが扶養できないのか、その理由(例:高齢、病気、経済的困窮など)を客観的な証拠とともに詳細に説明しなければなりません。「日本の子どもが扶養する以外に選択肢がない」という状況を明確に示すことが不可欠です。
扶養者の経済的能力に関する審査では、被扶養者の年間所得が一定額以下であることなどが基準となります。例えば、所得税法上の扶養親族となるには、原則として年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が103万円以下)である必要があります。この基準は、扶養親族の年齢などによって変動する場合があります。
また、健康保険の被扶養者となる場合は、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または一定の障害がある場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年収の半分未満であることが一般的です。ただし、この収入基準を満たしていても、その収入や貯蓄で生活費の大部分をまかなえる場合は、被扶養者として認定されないことがあります。審査では、継続的な収入があることを証明するために、課税証明書や在職証明書などが確認されることがあります。年収の目安や預貯金残高に関する明確な基準は公表されていません。
また、公的扶助に頼らずに医療費や介護費用などを負担できることを示す必要があるという情報も確認できませんでした。公的扶助は、資産や能力、その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対し、最低限度の生活を保障する制度です。そのため、扶養義務者による扶養は生活保護法による保護に優先されます。
老親扶養ビザは、親を日本に呼び寄せて扶養者が身の回りの世話をすることを前提としています。そのため、申請者である子と親が日本で同居することが必須の要件となります。単に生活費を送金するといった経済的な扶養だけでは認められません。
申請時には、親子が共に生活するのに十分な広さや設備を備えた住居が確保されていることを証明するために、賃貸借契約書や建物の登記事項証明書、間取り図などを提出します。子が親の生活を日常的に見守り、支えていくという実態が伴っていることが、審査において重視されます。
※無料相談はこちら
老親扶養ビザの申請手続きは、他の多くの在留資格とは異なる特殊な流れをたどります。一般的に、海外の日本大使館などでビザを取得してから来日しますが、この場合はまず親を「短期滞在」ビザで日本に招聘し、その後、日本国内の出入国在留管理局で「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うという手順を踏むのが通例です。このプロセスは複雑であり、計画的な準備が求められます。ここでは、申請から在留カードの取得までの流れを、大きく3つのステップに分けて解説します。
最初の手順は、親を「短期滞在」の在留資格で日本に呼ぶことです。国籍によってはビザが免除される場合もありますが、多くは日本の在外公館で観光や親族訪問を目的とする短期滞在ビザを申請します。その際、日本に住む子が身元保証人となり、招聘理由書や滞在予定表、身元保証書などの書類を準備する必要があります。この段階では、あくまで一時的な滞在が目的です。当初から在留資格の変更を目的としていると見なされると、短期滞在ビザの発給自体が認められない可能性もあるため、目的の伝え方には注意が求められます。
親が「短期滞在」で日本に入国した後、その在留期間が満了する前に、子の居住地を管轄する出入国在留管理局にて「特定活動」への在留資格変更許可申請を行います。これが実質的な老親扶養ビザの申請手続きとなります。この際に、在留資格変更許可申請書をはじめ、子の経済力を証明する書類、親との身分関係を証明する公的書類、そして最も重要となる「日本で扶養しなければならない人道上のやむを得ない理由」を詳述した理由書など資料を提出します。個々の事情に応じて必要な書類は異なるため、入念な準備と確認が必要です。
申請書類を提出すると、出入国在留管理局による審査が開始されます。審査期間はケースバイケースであり、数ヶ月から長い場合には1年以上かかることもあります。この間に、追加資料の提出を求められたり、申請内容について担当官から事情を聴取されたりする場合もあります。無事に許可されると、自宅に通知のハガキが届きます。そのハガキとパスポートなどの必要書類を指定された期間内に出入国在留管理局に持参し、手数料を納付することで、「特定活動」の在留資格が記された新しい在留カードが交付されます。
老親扶養ビザの申請では、なぜ日本での扶養が必要なのかという人道上の必要性と、扶養者の経済的な安定性を客観的に証明するため、非常に多くの書類を準備しなくてはなりません。提出書類は、扶養者である子が日本で準備するものと、被扶養者である親が母国で取得するものの両方が含まれます。
また、これらの定型的な書類に加え、個々の事情を審査官に理解してもらうための「理由書」の作成が極めて重要です。ここでは、申請に必要となる主な書類を分類して紹介します。
扶養者が用意する書類は、主にその身元、職業、経済力を証明するためのものです。具体的には、世帯全員が記載された住民票、在職証明書、所得と納税状況を示す課税証明書および納税証明書(通常は直近3年分)が基本となります。経済力を補強するためには、預貯金残高証明書も有効な場合があります。また、親と同居する住居を証明する書類としては、賃貸借契約書の写しなどが考えられます。これらの書類を通じて、親を扶養しても安定した生活を維持できるだけの経済的基盤があることを示すことが求められます。
海外にいる親が用意する書類は、本人確認と身分関係の証明、そして日本で扶養される必要性を示すものが中心です。パスポートの写しや証明写真はもちろんのこと、出生証明書など、扶養者との親子関係を公的に証明する書類が必要です。本国に配偶者がいないことを示すための死亡証明書や、他に扶養できる親族がいないことを説明する資料も重要となります。
また、健康上の理由で扶養が必要な場合は、病状や介護の必要性について具体的に記載された、本国の医師による診断書を準備します。これらの書類には、日本語の翻訳文を添付することが必須です。
理由書は、老親扶養ビザの申請において成否を分ける最も重要な書類と言えます。定型的な証明書類だけでは伝えきれない、申請に至った背景や人道上の必要性を、自身の言葉で具体的に説明するものです。内容には、親の現在の健康状態や本国での生活の困難さ、他に頼れる親族がいない具体的な状況、そして日本でなければならない理由などを、客観的な事実に基づいて詳細に記述します。
さらに、日本での生活設計や、親を経済的・精神的に支えていくという強い意志と覚悟を示すことも重要です。提出する他の証明書類と内容に矛盾がないよう、整合性を取りながら作成します。
老親扶養ビザは許可の基準が公表されておらず、取得が非常に難しい在留資格です。そのため、申請書類をただ提出するだけでは、許可を得ることは容易ではありません。審査官に「このケースは人道上、特別に在留を認めるべきだ」と判断してもらうためには、いくつかの重要なポイントを押さえた上で、説得力のある申請を行う必要があります。ここでは、厳しい審査を通過し、許可の可能性を少しでも高めるために、特に意識すべき3つのポイントを解説します。
審査において最も重要なのは、「なぜ他の国や地域ではなく、日本でなければならないのか」という点です。単に「親の面倒を見たい」という心情的な理由だけではなく、客観的な事実に基づいた具体的な理由を提示する必要があります。
例えば、親が患っている病気の専門的な治療が本国では受けられず、日本でしか治療法がない場合や、本国の政情不安や劣悪な生活環境により、親の生命や安全が脅かされている場合などが挙げられます。これらの人道上の理由を、医師の診断書や現地の状況を示す公的な資料など、信頼性の高い証拠を添えて詳細に説明することが不可欠です。
人道的な必要性が高くても、扶養者に親の生活を支える経済力がなければ許可は下りません。日本の社会保障制度に負担をかけず、親の生活費、住居費、医療費、将来的な介護費用まで、すべてを私費で賄えるだけの十分な経済力があることを、客観的な資料で明確に示す必要があります。年収を証明する課税証明書だけでなく、潤沢な預貯金があることを示す残高証明書や、安定した職業に就いていることを示す在職証明書などを複数提出し、経済的基盤が強固であることを多角的に証明します。将来にわたって安定的に扶養し続けられるという安心感を審査官に与えることが重要です。
老親扶養ビザの申請では、非常に多くの書類を提出する必要があるため、その準備には細心の注意が求められます。提出するすべての書類において、記載内容に不備や矛盾がないかを入念に確認することが不可欠です。例えば、理由書で説明している親の状況と、医師の診断書の内容が異なっているなど、整合性が取れていないと、申請全体の信憑性が損なわれます。また、海外で発行された書類には正確な日本語訳を添付する必要があるほか、証明書の有効期限にも注意しなくてはなりません。
老親扶養ビザ(特定活動)の在留資格を取得した後も、日本に在留し続けるためには定期的な更新手続きが必要です。このビザで最初に許可される在留期間は「1年」であることが一般的で、在留期限が切れる前(通常は3ヶ月前から)に、居住地を管轄する出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行わなくてはなりません。更新の審査では、初回の申請時に許可された状況が現在も継続しているかが重要なポイントとなります。特に、扶養者である子の収入や資産状況、親との同居の事実、親の健康状態などに大きな変化がないかどうかが確認されます。
もし、子の失業や収入の大幅な減少など、扶養能力に疑義が生じるような状況変化があった場合、更新が不許可となる可能性もあるため注意が必要です。
老親扶養ビザは、その性質上、申請が不許可となるケースも少なくありません。もし不許可の通知を受け取った場合は、まずその理由を正確に把握することが次のステップへの第一歩となります。通知書を持参して、申請した出入国在留管理局へ赴き、不許可理由の説明を求めましょう。理由を確認することで、申請内容のどの部分が要件を満たしていないと判断されたのか(例えば、経済力不足、人道上の必要性の立証不足など)が明らかになります。
その指摘された問題点を改善できる見込みがあれば、新たな証拠資料を追加するなどして、再申請を検討することが可能です。一度不許可になったとしても、理由を確認し、不備を補った上で再度挑戦する道は残されています。
老親扶養を目的とする「特定活動」ビザは、法律に明確な規定がなく、人道上の観点から個別に審査されるため、取得の難易度が非常に高い在留資格です。許可を得るには、親が原則70歳以上で、本国に配偶者や他に頼れる親族がいないこと、そして日本で扶養する子に、親の生活全般を支えうる十分な経済力があることを、客観的な証拠をもって立証しなくてはなりません。
申請手続きは、まず親を「短期滞在」で招聘し、日本国内で在留資格変更を行うという特殊な手順を踏みます。提出書類は多岐にわたるため、内容に矛盾がないよう入念に準備し、なぜ日本での扶養が不可欠なのかを理由書で具体的に訴えることが求められます。
※無料相談はこちら
70歳以上がひとつの目安ですが、絶対的な要件ではありません。70歳未満であっても、重篤な病気や障害などにより、一人での生活が著しく困難であり、人道上、日本での扶養が強く求められる特別な事情があれば、許可される可能性は皆無ではありません。扶養の必要性をより詳細かつ客観的に立証する必要があり、審査のハードルはさらに高くなります。
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで在留している場合、自身の在留資格の安定性も審査対象となるため、許可の難易度は格段に上がります。将来にわたって安定的に親を扶養し続けられるかという点で、永住者よりも厳しい目で見られる傾向があります。
老親扶養ビザの申請は非常に専門性が高く、個々の事情に応じた書類作成が求められます。行政書士などの専門家は、過去の事例や最新の審査傾向に関する知識が豊富です。そのため、個別の状況に最適な申請戦略を立て、説得力のある理由書の作成や証拠資料の収集をサポートしてくれます。複雑な手続きを任せることで、申請者の負担を軽減し、許可の可能性を高めることが期待されます。