
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
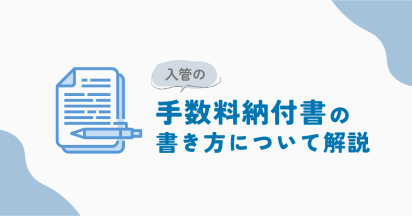
目次
出入国在留管理庁(入管)での在留資格に関する手続きでは、許可が下りた際に手数料納付書を提出します。この書類は、申請手数料を収入印紙を貼って、申請人の署名を以って納付したことを証明するためのものです。初めて手続きする方でも迷わないよう、手数料納付書の基本的な書き方を記入例に沿って解説します。正しい作成方法を理解し、スムーズな在留カード交付を進めましょう。
本記事では、入管の手数料納付書の書き方を簡単に解説していきます。
※無料相談はこちら
手数料納付書とは、在留資格の変更や更新といった各種申請が許可された際に、国へ手数料を納めるために使用する公式な書類です。手続きにかかる手数料は現金で直接支払うのではなく、手数料の金額に相当する収入印紙をこの用紙に貼り付けて提出することで納付します。したがって、申請が許可された場合にのみ必要となり、許可通知のハガキを受け取った後、新しい在留カードを受け取る際に他の書類とともに入管の窓口へ提出するのが一般的な流れです。
手数料納付書の記入を始める前に、必要なものをあらかじめ揃えておくと、手続きを円滑に進めることができます。
①手数料納付書の用紙:これは入管の窓口で受け取るか、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードして印刷します。
②記入用の黒のボールペン:消せるタイプのペンや鉛筆の使用は認められていません。
③手数料額分の収入印紙:郵便局や一部のコンビニエンスストアで購入できますが、コンビニでは高額な場合は取り扱いがないこともあるため郵便局での購入が推奨されます。
④許可通知のハガキなど、申請内容や手数料の金額がわかる書類:手元に置いておくと、記入ミスを防げます。
※詳細はこちら
手数料納付書の記入は、いくつかの項目を順番に埋めるだけで完了します。ここでは、具体的な書き方を見本に沿って5つのステップに分けて解説します。各ステップでどの部分に何を記入するのかを明確に説明するため、初めての方でも迷うことなく作成を進めることが可能です。一つひとつの項目を確実に確認しながら、正確な書類を準備していきましょう。
手数料納付書の用紙上部には、納付の目的となる申請の種類を選択する欄があります。「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」など、複数の選択肢が並んでいるため、自身が行った申請内容と一致する項目を探します。
該当する申請種類のチェックボックスに、チェックマーク(✓)を正確に入れてください。例えば、ビザの延長手続きを行った場合は「在留期間更新許可申請」にチェックします。どの申請に該当するかわからない場合は、入管から届いた許可通知のハガキで申請内容を確認できます。もし一覧に該当項目がない場合は、「その他」の欄に具体的な申請名を記入します。
申請の種類を選択する欄の隣、または下部には手数料の金額を記入するスペースがあります。ここには、納付する手数料の総額を算用数字で正確に記入してください。例えば、手数料が4,000円の場合は「4000」と記載します。この際、金額の前に「¥」マークを付けたり、3桁ごとにカンマ(,)を入れたりする必要はありません。
数字は誰が見ても明確に判読できるよう、丁寧にはっきりと書くことが求められます。手数料の金額は申請内容によって異なるため、許可通知のハガキや出入国在留管理庁のウェブサイトで事前に正しい金額を確認しておくことが不可欠です。
手数料納付書には、受付年月日を記入する欄も設けられています。この日付には、手数料納入書を実際に入管の窓口へ提出する年月日を記入するのが基本です。そのため、事前に家で記入するのではなく、提出当日に窓口で記入するのが最も確実な方法といえます。もし事前に記入する場合は、提出予定の日付を記載してください。日付の形式は和暦(令和〇年)でも西暦でも構いませんが、他の書類と表記を統一することが望ましいです。空欄のまま提出すると窓口で記入を求められることになるため、忘れずに記載するようにしましょう。
納付者氏名を記入する欄には、代理人ではなく申請者本人の名前を記載します。この記名は、在留カードやパスポートに記載されている氏名と完全に一致させる必要があります。漢字氏名を持つ方であれば漢字で、それ以外の方はアルファベットのブロック体でフルネームを丁寧に記入してください。この部分は本人が自筆で署名することが原則です。
手数料納付書の様式には、収入印紙を貼り付けるための大きな枠が印刷されています。納付する手数料の総額と同じ金額の収入印紙を、この枠内からはみ出さないように丁寧に貼り付けます。収入印紙の裏面を軽く水で湿らせると接着できます。もし複数の収入印紙を組み合わせて手数料額にする場合は、印紙同士が重ならないように並べて貼りましょう。注意点として、貼り付けた収入印紙に自分で消印(割印)をしてはいけません。消印は入管の職員が行うものです。
手数料納付書の記入は比較的簡単ですが、書き損じた場合の訂正方法や収入印紙の購入場所など、細かな点で疑問が生じることがあります。ここでは、手続きを円滑に進めるために、よく寄せられる質問とその回答、そして注意すべき点をまとめました。事前にこれらの情報を確認しておくことで、当日の窓口での混乱や書類の不備を防ぎ、安心して手続きに臨むことができます。
手数料納付書の記入内容を間違えた場合、修正液や修正テープの使用は避けてください。公的な書類では、修正の履歴がわかるように訂正することが基本です。軽微な書き損じであれば、誤った箇所に二重線を引き、その上部などの余白に正しい内容を記載します。訂正箇所に訂正印を押す必要は必ずしもありませんが、より丁寧な訂正方法となります。ただし、氏名や金額といった重要な部分を大きく間違えたり、用紙全体が汚れたりした場合は、新しい用紙に書き直すのが推奨される方法です。
収入印紙は、全国の郵便局の窓口で購入するのが最も確実です。入管手続きで必要となる4,000円や8,000円といった比較的高額な額面も、郵便局であれば問題なく取り扱っています。また、一部のコンビニエンスストアでも購入可能ですが、200円などの低額な収入印紙しか置いていない場合や、在庫がないケースも多いため注意が必要です。多くの出入国在留管理局の庁舎内やその近隣には、収入印紙を販売する売店が設けられていることが多いため、手続き当日に現地で購入することもできます。ただし、売店が混雑している可能性も考慮し、事前に郵便局などで用意しておくとスムーズです。
納付すべき手数料の正確な金額がわからない場合、いくつかの方法で確認できます。最も確実なのは、申請許可後に入管から郵送されてくる通知ハガキを確認する方法です。このハガキには、手続きの種類とともに必要な手数料の金額が明記されています。もしハガキを紛失してしまった場合や、事前に金額を知りたい場合は、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトを参照してください。サイト内には各種手続きの手数料に関する情報が一覧で掲載されています。正しい金額の収入印紙を準備するために、必ず事前に確認しましょう。
手数料納付書の用紙は、複数の方法で手に入れることができます。最も一般的なのは、地方出入国在留管理局やその支局、出張所の窓口で直接受け取る方法です。通常、申請書類が置かれているコーナーに用意されているため、誰でも自由に入手できます。また、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトからもPDF形式でダウンロードが可能です。これを自宅やコンビニエンスストアのプリンターでA4サイズの普通紙に印刷して使用することもできます。事前にウェブサイトから入手して記入を済ませておけば、当日の手続きにかかる時間を短縮できるという利点があります。
行政書士などの専門家に手続きを依頼している場合は、通常、事務所側で用紙を準備します。
入管へ提出する手数料納付書は、納付目的、手数料額、提出日、氏名を正しく記入し、指定された金額の収入印紙を貼り付けて作成します。用紙は各地方出入国在留管理局の窓口や公式ウェブサイトで入手し、収入印紙は郵便局などで購入します。
書き損じた際は修正液などを使用せず、二重線で訂正するか新しい用紙に書き直すのが基本です。許可通知を受け取った後、これらの手順に従って正確に書類を準備することで、在留カードの受け取りなどの手続きを不備なく進めることができます。
※無料相談はこちら