
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
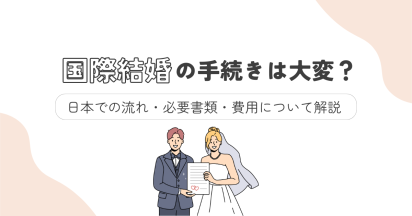
目次
国際結婚の手続きは、日本人同士の結婚と比べて用意すべき書類が多く、プロセスが複雑なため大変だと感じられることがあります。特に、日本での手続きの具体的な流れや、パートナーの国籍によって異なる必要書類、そして全体でかかる費用について不安を持つ方は少なくありません。しかし、事前に全体の流れを把握し、計画的に準備を進めることで、手続きは決して乗り越えられないものではありません。
本記事では、国際結婚の手続きに関する網羅的な情報を提供し、具体的な進め方を解説します。
※無料相談はこちら
日本で国際結婚をするには、大きく分けて4つの手順を踏む必要があります。
・日本人と外国人パートナー双方の必要書類を不備なく揃えること
・日本の市区町村役場へ婚姻届を提出し、法的に婚姻を成立させる
・相手の国の大使館や領事館へ報告的な届出を行う
・パートナーが日本で暮らすために必要な配偶者ビザを申請する
この一連の方法を理解し、各ステップを確実に進めていくことが、国際結婚をスムーズに成立させるための鍵となります。
※詳細はこちら
国際結婚の手続きにおいて、最も重要かつ複雑なのが書類の準備です。日本人側と外国人側でそれぞれ必要な書類が異なり、特に外国人パートナーの書類は、国籍によって準備するものが大きく変わります。
一般的に、日本人側は戸籍謄本、外国人側はパスポートや出生証明書、そして婚姻要件具備証明書などが必要です。これらの書類に不備があると手続きが滞る原因となるため、事前に提出先の市区町村役場や相手国の在日大使館にしっかりと確認し、漏れなく揃えることが求められます。
日本人側が用意する最も基本的な書類は戸籍謄本です。これは、本籍地のある市区町村役場で取得できます。結婚歴の有無や身分関係を証明するために提出が求められ、通常は発行から3ヶ月以内のものが有効とされています。本籍地が遠方の場合は、郵送での取り寄せも可能です。
婚姻届を提出する役所が本籍地と同じであれば不要な場合もありますが、国際結婚では審査が慎重に行われるため、事前に提出先の役所に確認しておくと確実です。日本の法律に基づき婚姻手続きを進める上で、この戸籍謄本は不可欠な書類となります。
外国人パートナーが用意すべき書類は多岐にわたります。
・国籍を証明するためのパスポート
・出生証明書:必要となる場合が多く、これは相手の本国から取り寄せる必要があります。
これらの海外の公的機関が発行した書類は、原則として日本語の翻訳文を添付することが求められます。翻訳は誰が行っても良い場合が多いですが、翻訳者の氏名と連絡先を明記する必要がある点に注意が必要です。海外から書類を取り寄せるには時間がかかるため、早めに相手と協力して準備を始めることが肝心です。
婚姻要件具備証明書とは、外国人パートナーが母国の法律で定められた結婚の条件を満たしており、独身であることを証明する公的な書類です。この証明書は、重婚を防ぐ目的で日本の役所に提出が求められます。取得方法は国によって異なり、在日大使館や領事館で発行される場合もあれば、本国の役所でしか発行できないケースも存在します。この証明書がなければ、日本での婚姻手続きを進めることはできません。将来的に法的な夫婦として認められるための第一歩となる重要な書類であり、必ず準備が必要です。
※詳細はこちら
日本で国際結婚を成立させるための具体的な手続きの流れを、ステップごとに詳しく見ていきます。書類の準備から婚姻届の提出、相手国への報告、そして配偶者ビザの申請まで、一連のプロセスを順を追って理解することで、全体像を把握しやすくなります。各ステップで注意すべき点も合わせて確認し、スムーズな手続きを目指しましょう。
最初に行うべきことは、日本人と外国人パートナー双方の必要書類をすべて揃えることです。
日本人側は戸籍謄本、外国人側はパスポート、出生証明書、婚姻要件具備証明書などが基本となります。特に外国人側の書類は、国籍によって必要となるものが異なるため、事前に相手の国の在日大使館や、婚姻届を提出する日本の市区町村役場に問い合わせて、正確な情報を確認することが不可欠です。書類に不備があると受理されないため、翻訳文の添付が必要か、証明書の有効期限は切れていないかなど、細部まで入念にチェックしてください。
必要書類がすべて揃ったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。提出先は、日本人の本籍地または住所地、あるいは外国人パートナーの住所地のいずれかの役所です。
例えば大阪市に住んでいる場合は、大阪市内の区役所が提出先となります。婚姻届には、成人2名の証人の署名が必要です。国際結婚の場合、書類の審査に時間がかかることがあり、即日受理ではなく「受理伺い」として預かり扱いになるケースも少なくありません。特に外国の書類に不備がないか、法務局への照会が必要になる場合もあるため、時間に余裕を持って市役所や区役所へ向かうことが推奨されます。
日本の役所で婚姻届が受理され、法的に結婚が成立した後、次に相手の国への報告手続きが必要です。この報告的届出は、相手国の在日大使館や領事館で行います。この手続きを行わないと、日本では夫婦として認められていても、相手の国では独身のままという状況になってしまいます。
提出する書類は国によって異なりますが、一般的には婚姻届受理証明書や、婚姻の事実が記載された日本の戸籍謄本、そしてそれらの書類の外務省による認証(アポスティーユなど)が必要となる場合があります。手続き完了後、相手の国でも法的に夫婦として登録されます。
両国での婚姻手続きが完了したら、外国人パートナーが日本に住むために「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)を申請します。このビザがなければ、外国人パートナーは日本で長期的に生活することができません。申請は、原則として地方出入国在留管理局で行います。審査では、偽装結婚ではないこと、そして日本で安定した生活を送れる経済力があるかどうかが厳しく見られます。
交際の経緯を説明する書類や、二人の写真、所得を証明する書類など、多くの資料を提出する必要があり、入念な準備が求められます。
外国人パートナーがすでに留学や就労などの在留資格で日本に住んでいる場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
例えば、留学生として滞在している韓国人や、技術・人文知識・国際業務ビザで働く中国人と結婚した場合などがこれに該当します。
この申請が許可されると、現在の在留資格が「日本人の配偶者等」に変更されます。フィリピン人と結婚し、相手がすでに技能実習などで日本に滞在しているケースも同様です。申請は地方出入国在留管理局で行い、現在の在留資格の期限が切れる前に手続きを完了させる必要があります。
韓国人と結婚する場合でも、他の国籍の方と同様に手続きは必須です。
外国人パートナーが海外に住んでいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を日本の地方出入国在留管理局に行います。この申請は、日本にいる配偶者が代理で行うのが一般的です。
証明書が交付されたら、それを海外にいるパートナーに郵送します。パートナーはその証明書を現地の日本大使館や領事館に持参し、査証(ビザ)の発給申請を行います。査証が発給されると、それを使って来日し、空港で在留カードが交付されることで、日本での生活を始めることができます。このプロセスは数ヶ月を要することが多いです。
国際結婚の手続きにかかる費用は、書類の取得費用、翻訳料、交通費などが主です。戸籍謄本や婚姻届受理証明書などの発行手数料は数百円程度ですが、海外から書類を取り寄せる場合は、国際郵便料金や現地での発行手数料がかかります。また、書類の翻訳を専門業者に依頼すると、1通数千円から1万円程度が相場です。
配偶者ビザの申請自体には手数料はかかりませんが、行政書士などの専門家に手続きの代行を依頼する場合は、10万円から20万円程度の報酬が必要です。
不安な点があれば専門家に相談することも一つの選択肢です。
※無料相談はこちら
国際結婚の手続きが完了するまでの期間は、ケースバイケースであり一概には言えません。書類の準備から婚姻届の提出、相手国への報告、そして配偶者ビザの取得まで、すべてのプロセスを合わせると、半年から1年以上かかることも珍しくありません。特に、海外からの書類取り寄せや、配偶者ビザの審査には時間がかかる傾向があります。
スムーズに進めば数ヶ月で完了することもありますが、書類の不備や追加資料の要求などがあれば、期間はさらに延びる可能性があります。
日本の役所に婚姻届を提出してから受理されるまでの時間は、提出する役所や書類の状況によって大きく異なります。日本人同士の結婚であれば、書類に不備がなければ即日受理されるのが一般的です。しかし、国際結婚の場合は、外国人パートナーの提出書類に不備がないか、本国の法律に照らし合わせて問題がないかなどを慎重に審査するため、数日から数週間、場合によっては1ヶ月以上かかることもあります。特に、婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合、法務局への照会が必要となり、審査に長期間を要する傾向があります。
配偶者ビザの審査にかかる期間は、出入国在留管理庁が公表している標準処理期間によると、在留資格認定証明書交付申請の場合は1ヶ月から3ヶ月、在留資格変更許可申請の場合は2週間から1ヶ月とされています。ただし、これはあくまで目安であり、申請者の状況や提出書類の内容、申請時期によって審査期間は大きく変動します。
審査が難航するケースでは、半年以上かかることもあります。結婚の信憑性に疑義がある場合や、収入面に不安があると判断された場合は、追加資料の提出を求められ、審査が長期化する一因となります。
国際結婚の手続きは複雑で時間がかかるため、いくつかの注意点を押さえることで、よりスムーズに進めることが可能です。パートナーとの密な連携はもちろんのこと、必要に応じて専門家のサポートを受けることも有効な手段です。事前の情報収集と計画的な準備が、手続きを円滑に進めるための鍵となります。
国際結婚で最も注意すべき点は、パートナーの国籍によって必要書類や手続きが大きく異なることです。例えば、韓国や台湾のように戸籍制度がある国と、アメリカやオーストラリアのように戸籍制度がない国では、用意する書類が変わります。中国のように、婚姻要件具備証明書ではなく、公証処で発行される「未婚証明書」が必要な場合もあります。
また、フィリピンやタイ、ベトナム、インドネシア、インドといったアジア諸国では、独自の証明書や手続きが求められるケースが見られます。ロシアやイタリアなど、国ごとに法律や制度が違うため、必ず事前に相手国の在日大使館や日本の役所に確認することが重要です。
準備する証明書類の多くには、有効期限が設定されている点に注意が必要です。日本の戸籍謄本や住民票は、一般的に発行から3ヶ月以内、場合によっては6ヶ月以内のものを求められます。
同様に、外国人パートナーが用意する婚姻要件具備証明書や出生証明書などにも、有効期限が設けられていることがほとんどです。せっかく書類を揃えても、提出時に有効期限が切れていては受理されません。すべての書類の有効期限をしっかりと管理し、期限内に手続きを終えられるよう、計画的に準備を進めることが求められます。
国際結婚の手続きは、予測できない事態が発生しやすいものです。海外からの書類の取り寄せに想定以上の時間がかかったり、役所での審査が長引いたり、配偶者ビザの申請で追加書類を求められたりすることがあります。
そのため、スケジュールはぎりぎりで組むのではなく、あらゆる可能性を考慮して十分に余裕を持たせることが大切です。特に、パートナーの在留期限が迫っている場合や、結婚後にすぐに同居を始めたいと考えている場合は、早め早めの行動を心がけ、計画的に手続きを進めていく必要があります。
日本での国際結婚の手続きは、日本人同士の結婚に比べて手順が多く、必要書類も複雑です。
しかし、事前に全体の流れを把握し、一つ一つのステップを着実に進めていけば、乗り越えることは十分に可能です。パートナーの国籍による違いを理解し、時間に余裕を持って計画を立てることが成功の鍵です。この記事で解説した情報を参考に、パートナーと協力しながら準備を進めてください。
※無料相談はこちら